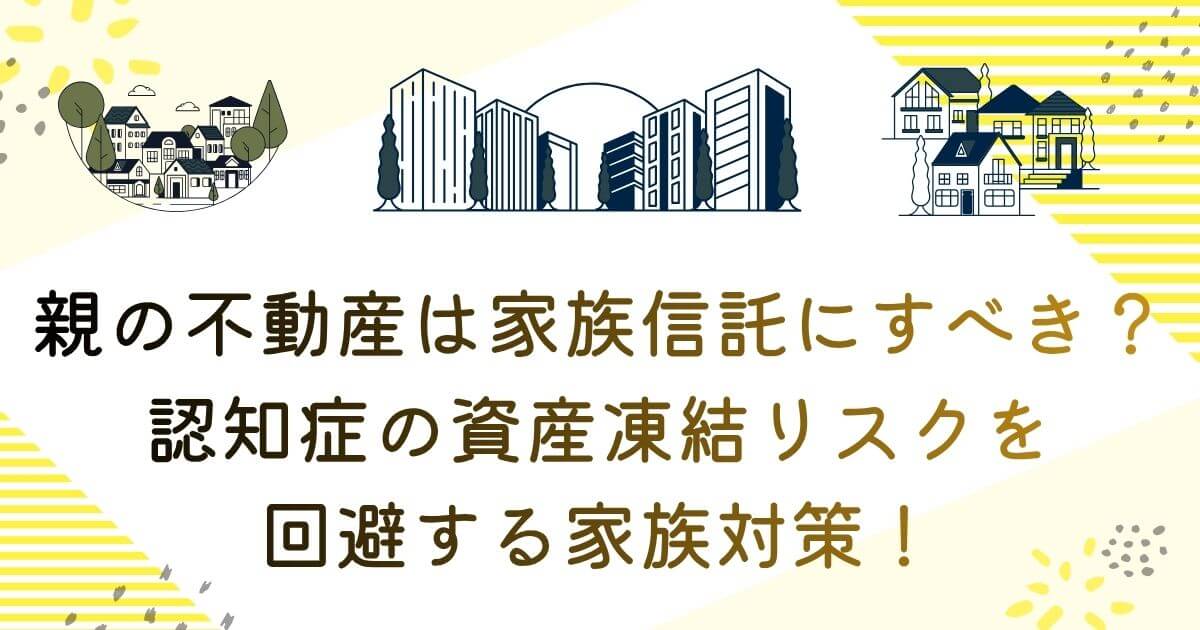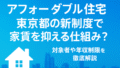導入文(リード文)
親の不動産をどうするか――。
相続登記が義務化(2024年4月施行)となり、認知症も気になってきた…
「親が元気なうちに準備を始めよう」と考える家庭が急増しています。
しかし実際に調べてみると、
家族信託ってどんな仕組み?
遺言書や成年後見制度と何が違う?
不動産を信託すると名義はどうなるの?
…といった疑問が次々に出てきます。
本記事では、不動産歴40年でFPでもある私が、初心者でも理解できるように解説します。
- 家族信託の仕組み
- 親の不動産を家族信託にすべき5つの理由
- 注意点・費用・失敗事例
を順に紹介していきます。
この記事を読むことで、「家族信託を使えばどんなメリットがあるのか」「ご自身の家庭に向いているのか」が明確になります。
そもそも「家族信託」とは?仕組みをわかりやすく解説
親の不動産を家族信託にする前に、まずは基本の仕組みを理解しておきましょう。
家族信託とは、家族に資産を託して管理してもらう制度
家族信託とは、親(委託者)が子ども(受託者)など信頼できる家族に資産の管理を任せる制度です。
契約によって、不動産や預金などの管理・運用・処分を受託者が行い、親の生活や介護資金の確保に活用できます。
たとえば、親名義の家を子どもが管理・売却できるようにしておくことで、
認知症になってもスムーズに対応できるのが最大の特徴です。
不動産の所有者
契約に基づき運用
信託財産の収益
委託者(親)と受託者(子)が信託契約を結ぶ
不動産の名義を受託者に変更(登記)
受託者が契約内容に従って不動産を管理
受益者(親)が家賃収入や売却益を受け取る
✓ 親が認知症になっても、子が契約に基づいて管理・売却できる
✓ 贈与税は原則かからない(委託者=受益者の場合)
なぜ今、家族信託が注目されているのか
高齢化に伴い、認知症による「財産凍結問題」が深刻化しています。
また、2024年からは相続登記の義務化がスタートし、「名義をそのままにしておく」ことがリスクになっています。
こうした背景から、“生前のうちに対策できる制度”として、家族信託のニーズが急上昇しているのです。
なぜ「親の不動産」を家族信託にした方がいいのか?5つの理由
① 認知症による資産凍結を回避できる
親が認知症になると、法律上は「判断能力を失う」とされ、不動産を売る・貸す・登記するなどの手続きができません。
銀行口座も凍結され、介護費用を支払えないケースもあります。
家族信託を設定しておけば、親が判断能力を失っても、受託者(子ども)が契約に基づいて管理・売却を行えるため、生活資金や施設費用を確保できます。
- 介護資金が足りない:自宅を売却できず施設費用が払えない
- 空き家の放置:老朽化が進み近隣トラブルや固定資産税の負担増
- 相続時の混乱:名義変更ができず相続人間で争いが発生
- 機会損失:良い買い手が現れても売却のチャンスを逃す
- 後見人費用の継続負担:月2〜6万円の報酬が本人が亡くなるまで発生し続ける
② 不動産の管理・売却がスムーズになる
「親の家を将来的に売って介護資金にしたい」というケースでは、家族信託が非常に有効です。
信託契約を結んでおけば、受託者が契約の範囲内で不動産を処分できるため、手続きが止まる心配がありません。
また、共有名義の不動産や複数の相続人が関係する場合でも、信託契約で権限を明確にしておくことでトラブルを防げます。
③ 相続トラブルを防ぎ、家族の負担を軽減できる
相続時には、「誰が何を相続するか」で争いになることが少なくありません。
家族信託では、親が生前に「どの財産を誰のために使うか」を契約で決められるため、相続時の揉め事を未然に防ぐことができます。
また、信託契約書に「親の死亡後は長男が管理を続ける」などのルールを盛り込むことも可能です。
④ 相続登記義務化に対応できる
2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。
登記を怠ると過料(罰金)の対象になるため、事前に信託契約をして管理権限を整理しておくことで、登記手続きの混乱を防げます。
特に高齢の親名義で不動産を持っている場合は、信託契約で早めに権限を移しておくことがリスク回避につながります。
⑤ 成年後見制度よりも柔軟で実用的
成年後見制度は裁判所の監督下で行われるため、手続きや報告義務が多く、費用もかかります。
家族信託は契約ベースで進められるため、自由度が高く・家族の意思を反映しやすいのが大きなメリットです。
家族信託のデメリット・注意点
家族信託は万能ではありません。利用する前に次のような注意点を理解しておきましょう。
費用がかかる
契約書の作成、公証役場での認証、不動産登記の費用、専門家への報酬などが発生します。
一般的な目安は 30万〜80万円程度です。財産の内容や専門家によって変わります。
税金の扱いが複雑になる場合がある
不動産を信託する際には、贈与税や登録免許税の対象になるケースがあります。
税理士や司法書士に相談して、節税・贈与のリスクを事前に確認しておくことが重要です。
信頼できる受託者を選ぶ必要がある
信託財産を実際に管理するのは「受託者」です。
金銭管理能力や誠実さが欠けていると、トラブルにつながる恐れがあります。
契約時には信頼できる家族を選ぶことが最重要です。
遺言書・成年後見制度との違い
| 制度名 | 主な目的 | 開始時期 | 管理の柔軟性 | 裁判所の関与 |
| 家族信託 | 財産管理・運用 | 生前から可能 | 高い | なし |
| 遺言書 | 死後の財産分配 | 死後 | 低い | なし |
| 成年後見制度 | 判断能力喪失後の管理 | 認知症発症後 | 低い | あり |
家族信託は「生前から始められる」「契約内容を自由に決められる」という点で、他制度よりも実用的です。
一方で、遺言書や成年後見と組み合わせて使うと、より安心できる資産管理が可能になります。
家族信託の費用と手続きの流れ
手続きのステップ
- 家族で話し合い、信託する財産と目的を決める
- 専門家(司法書士・弁護士・行政書士など)に相談
- 信託契約書の作成・内容確認
- 公証役場で認証
- 不動産の名義変更・登記
全体の期間は 1〜2か月程度 が目安です。
費用の内訳
| 項目 | 費用目安 |
| 契約書作成・相談料 | 10〜30万円 |
| 公証役場手数料 | 5〜10万円 |
| 登録免許税・登記費用 | 10〜20万円 |
| 税理士・司法書士報酬 | 10〜30万円 |
よくあるトラブルと予防策
受託者の管理ミス・横領
→ 予防策:複数受託者(兄弟など)を設定し、相互チェックできる仕組みにする。
契約内容の不備
→ 予防策:専門家(司法書士・弁護士)に契約書をチェックしてもらう。
家族間の認識ズレ
→ 予防策:信託契約前に家族全員で話し合い、目的を共有する。
まとめ|親の不動産を守るなら、早めの家族信託がおすすめ
家族信託は、親の財産を「守る」だけでなく、
家族が安心して生活を続けるための仕組みです。
特に、
- 認知症リスクがある親が不動産を所有している
- 相続登記義務化に備えたい
- 相続トラブルを避けたい
という家庭では、早めの検討が何より重要です。
家族信託は、「将来の安心を今つくる」ための制度です。
一度、司法書士や弁護士などの専門家に相談し、家族に最適な形を整えておきましょう。