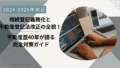リード文
親から相続した地方の実家。思い出の詰まった家ですが、誰も住む予定がなく、固定資産税や管理の負担だけが残っている――。そんな悩みを抱えている方は少なくありません。
「売却したいけれど、地方の古い家なんて買い手がつくのだろうか」
「不動産会社に相談しても、安い物件だからと断られるのでは」
実際、売却価格が低い物件は、不動産会社にとって仲介手数料が少なく、積極的に動いてもらいにくいという現実があります。しかし、2018年から始まった「低廉な空き家等の媒介報酬特例」という制度によって、この状況が変わりつつあるのです。
この記事では、不動産業界で40年の経験を持つ私が、相続した実家の売却で知っておくべき媒介報酬特例の内容から、実際の売却ステップ、よくある失敗例まで、わかりやすく解説します。空き家を放置するリスクから解放され、適切な選択をするための判断材料として、ぜひ最後までお読みください。
・低価格の実家が売れにくい理由と特例制度の仕組み
・媒介報酬特例が使える物件の条件と具体的なメリット
・実家売却を成功させる具体的な5つのステップ
・売却以外の選択肢との比較検討ポイント
相続した実家が売れない3つの理由
相続した実家を売却しようとしても、なかなか話が進まない。そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。地方の実家が売れにくい背景には、明確な理由があります。
理由1:地方の不動産市場の縮小
少子高齢化と都市部への人口集中により、地方の不動産需要は年々減少しています。特に駅から遠い、商業施設が少ないといった立地では、購入希望者を見つけること自体が困難です。
空き家率も深刻で、総務省の調査によれば全国の空き家率は13.8%で過去最高を記録しています。地方ではさらに高く、20%を超える自治体も珍しくありません。つまり、5軒に1軒が空き家という状況なのです。
参考サイト
- 総務省統計局 公式データ(PDF)
- 総務省統計局 調査結果ページ
理由2:低価格物件は不動産会社が敬遠する
不動産会社のビジネスモデルを理解すると、この問題の本質が見えてきます。不動産仲介の収入源は「仲介手数料」です。この手数料は、売買価格に応じて上限が決められています。
通常の仲介手数料の上限は以下の通りです。
- 売買価格200万円以下の部分:5%+消費税
- 売買価格200万円超400万円以下の部分:4%+消費税
- 売買価格400万円超の部分:3%+消費税
例えば、300万円の物件を売却した場合、仲介手数料の上限は約14万円(税込15.4万円)です。一方、3,000万円の物件なら約100万円(税込110万円)となります。
不動産会社にとって、低価格物件の仲介は手間は同じでも収入が少ないため、どうしても後回しにされがちなのです。
理由3:建物の老朽化と維持管理の問題
相続した実家の多くは築30年、40年以上経過しています。雨漏り、シロアリ被害、給排水設備の老朽化など、修繕が必要な箇所が多く、そのままでは買い手がつきません。
かといって、リフォームするにも数百万円の費用がかかります。売却価格が低い物件では、リフォーム費用を回収できない可能性が高く、投資判断が難しいのです。
また、相続人が遠方に住んでいる場合、定期的な管理も負担になります。草刈り、換気、水道の通水など、放置すれば建物の劣化は加速し、ますます売却が難しくなる悪循環に陥ります。
「低廉な空き家等の媒介報酬特例」とは?
こうした低価格物件の流通を促進するために創設されたのが「低廉な空き家等の媒介報酬特例」です。この制度について、詳しく見ていきましょう。
特例の基本内容
この特例は、2018年1月に国土交通省が告示した制度で、正式には「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の特例措置といいます。
制度創設の背景
全国で増え続ける空き家問題の解決策として、低価格の空き家でも不動産会社が積極的に仲介できるよう、報酬体系を見直したものです。従来の仲介手数料では採算が合わないという不動産会社の実情を踏まえ、売主から受け取れる報酬額の上限を引き上げました。
2024年7月には、さらなる空き家流通促進のため、対象物件の価格上限と報酬上限が大幅に拡充されています。
対象となる物件の基本条件(2024年7月改正後)
- 売買価格が800万円以下の宅地または建物
- 空き家またはこれから空き家になる予定の物件
- 現地調査等の費用が通常よりかかる物件
通常の仲介手数料との違い
通常の仲介手数料に加えて、現地調査等にかかる費用を売主から受け取ることができます。2024年7月の改正により、報酬の上限額は売主から30万円(税抜)=33万円(税込)、買主からも同額を受け取ることが可能になりました。
重要なのは、この特例を適用するには事前に売主・買主の承諾が必要という点です。不動産会社は契約前に、特例を適用すること、かかる費用の内訳、報酬額を明確に説明しなければなりません。
【重要】2024年7月の制度改正について
旧制度:400万円以下 → 新制度:800万円以下2. 報酬の上限額が引き上げ
旧制度:18万円(税抜) → 新制度:30万円(税抜)=33万円(税込)3. 買主からも報酬を受け取れるように
旧制度:売主からのみ → 新制度:売主・買主それぞれから最大33万円(税込)
改正による実質的な変化
この改正により、不動産会社は売主・買主の両方から報酬を受け取ることで、最大で66万円(税込)の報酬を得ることが可能になりました。これにより、以前よりさらに積極的な売却活動が期待できるようになっています。
注意点
この特例を適用する場合、不動産会社は媒介契約締結時に、報酬額について売主・買主に事前に説明し、合意を得る必要があります。2024年7月1日以降に締結される媒介契約、または既存の媒介契約を更新する際に、この新制度が適用されます。
特例による報酬額の具体例(2024年7月改正後)
新制度では、より幅広い価格帯の物件が対象になりました。実際の売却価格別に、仲介手数料がどう変わるのか見てみましょう。
【旧制度】
通常の仲介手数料:10万円(税抜)
特例適用時(売主から):18万円(税抜)
差額:8万円アップ【新制度(2024年7月〜)】
通常の仲介手数料:10万円(税抜)
特例適用時(売主から):30万円(税抜)=33万円(税込)
特例適用時(買主から):30万円(税抜)=33万円(税込)
不動産会社の合計報酬:最大66万円(税込)
【旧制度】
特例対象外(通常の仲介手数料のみ:約23万円)【新制度(2024年7月〜)】
特例適用時(売主から):30万円(税抜)=33万円(税込)
特例適用時(買主から):30万円(税抜)=33万円(税込)
不動産会社の合計報酬:最大66万円(税込)
【旧制度】
特例対象外(通常の仲介手数料のみ:約30万円)【新制度(2024年7月〜)】
特例適用時(売主から):30万円(税抜)=33万円(税込)
特例適用時(買主から):30万円(税抜)=33万円(税込)
不動産会社の合計報酬:最大66万円(税込)
売主にとってのメリット
「仲介手数料が高くなるなら、売主には不利では?」と思われるかもしれません。しかし、この特例には大きなメリットがあります。
1. 不動産会社が積極的に動いてくれる
報酬が確保できるため、低価格物件でも真剣に売却活動をしてくれます。
2. 丁寧な現地調査をしてもらえる
建物の状態、境界、権利関係など、詳細な調査が期待できます。
3. 売却の可能性が高まる
そもそも仲介を受けてもらえなければ売却できません。数万円の差で売却が実現できるなら、結果的に得です。
私の経験では、特例を活用して200万円台の空き家が3ヶ月で売却できた事例もあります。従来なら「仲介は難しい」と断られていたような物件です。
この特例が使える物件・使えない物件
特例を活用するには、いくつかの条件があります。自分の物件が対象になるか、確認しておきましょう。
対象となる条件
1. 売買価格が800万円以下
2024年7月の改正により、対象物件の価格上限が400万円から800万円に引き上げられました。これにより、より多くの物件が特例の対象となっています。
土地と建物を合わせた売買価格が800万円以下であれば、この特例を利用できます。
注意したいのは、査定額ではなく「実際の売買価格」で判断される点です。当初900万円で売り出して売れず、後から750万円に値下げした場合は特例の対象になります。
2. 空き家または空き家になる予定の物件
- 現在誰も住んでいない空き家
- 売買契約の締結までに空き家になることが確実な物件
相続した実家で、親が施設に入所して誰も住んでいない場合や、売却が決まり次第引っ越す予定の場合も含まれます。
3. 現地調査等の費用が発生する
不動産会社が実際に現地調査、測量、権利関係の調査などを行う必要がある物件です。単に写真を撮って物件情報を掲載するだけでは特例の対象になりません。
地域の制限はあるか
基本的に全国どこでも適用可能です。ただし、自治体によっては空き家バンクとの連携を条件にしている場合もあります。事前に地元の不動産会社や自治体に確認しておくと良いでしょう。
注意すべきポイント
両手仲介の場合の扱い
不動産会社が売主と買主の両方から仲介を依頼される「両手仲介」の場合、新制度では売主・買主それぞれから最大33万円(税込)を受け取ることができます。
つまり、不動産会社は最大で66万円(税込)の報酬を得られるため、従来以上に積極的な売却活動が期待できます。これにより、800万円以下の空き家でも、しっかりとした広告活動や丁寧な顧客対応が行われる可能性が高まりました。
必ず事前説明と承諾が必要
特例を適用するには、媒介契約を結ぶ前に、不動産会社から以下の説明を受け、書面で承諾する必要があります。
- 特例を適用すること
- 現地調査等の内容
- 報酬額の具体的な金額(売主・買主それぞれからいくら受け取るか)
2024年7月の改正により、この事前説明と合意の重要性がさらに明確化されました。説明なく高額な請求をされた場合は、宅地建物取引業法違反の可能性があります。契約書類をしっかり確認しましょう。
上限33万円(税込)を超える請求はNG
2024年7月の改正後も、売主から受け取れる報酬の上限は30万円(税抜)=33万円(税込)です。買主からも同様に最大33万円(税込)までです。それ以上の請求があった場合は、違法な可能性があります。
ただし、測量費用や解体費用など、媒介報酬とは別の「実費」として請求される場合もあります。これらは報酬とは別枠ですが、事前に明確な説明と見積もりが必要です。不明瞭な請求には注意しましょう。
実家売却を成功させる5つのステップ
特例の仕組みが分かったところで、実際にどのように売却を進めていけば良いのか、具体的なステップを見ていきましょう。
ステップ1:物件の現状確認
まず、売却する物件の状況を正確に把握することから始めます。
建物の状態チェック
- 雨漏り、シロアリ被害の有無
- 給排水設備の状態
- 外壁や屋根の劣化具合
- 室内の傷みや汚れの程度
可能であれば、一度現地を訪れて写真や動画を撮影しておくと、後の査定や売却活動で役立ちます。
権利関係の整理
- 登記簿謄本の取得(法務局で入手可能)
- 相続登記は完了しているか
- 抵当権などの担保権は設定されていないか
- 境界は明確か、隣地との紛争はないか
特に相続登記が未完了の場合は、先に登記を済ませる必要があります。2024年4月から相続登記が義務化されましたので、放置せず早めに対応しましょう。
以下のブログ記事に相続登記の義務化についての解説がありますので、ご参考にしてください。
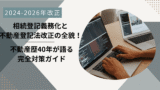
固定資産税の確認
固定資産税の納税通知書を確認し、年間の税負担額を把握しておきます。これは売却の緊急度を判断する材料になります。
ステップ2:不動産会社選び
特例を活用するには、制度を理解している不動産会社を選ぶことが重要です。
特例に対応している会社の見つけ方
1. 地元の不動産会社に問い合わせる
「低廉な空き家の媒介報酬特例に対応していますか?」と直接聞きましょう。
2. 自治体の空き家相談窓口に相談する
多くの自治体で空き家対策の相談窓口があり、協力業者を紹介してもらえます。
3. 空き家バンクと連携している業者
自治体の空き家バンクに登録している不動産会社は、特例にも詳しい傾向があります。
複数社への相談の重要性
必ず2〜3社に査定を依頼しましょう。価格だけでなく、以下の点も比較します。
- 特例の説明が明確で分かりやすいか
- 売却戦略が具体的か(空き家バンク、リフォーム提案など)
- レスポンスの速さと丁寧さ
- 過去の空き家売却実績
私の経験上、「とにかく早く売りましょう」と急がせる会社より、現状分析をしっかりして複数の選択肢を提示してくれる会社の方が信頼できます。
ステップ3:査定と価格設定
不動産会社から査定額が提示されたら、その根拠をしっかり確認します。
適正価格の見極め方
- 近隣の売却事例:同じエリアで似た条件の物件がいくらで売れたか
- 固定資産税評価額:一般的に市場価格の7割程度とされています
- 土地と建物の内訳:建物が古い場合、土地価格がメインになります
地方の空き家は、建物の価値がほぼゼロで、土地だけの価格になることも珍しくありません。「思ったより安い」と感じるかもしれませんが、市場の実勢価格を受け入れることも大切です。
高すぎる価格設定は、いつまでも売れ残る原因になります。売却期間が長引けば、その間も固定資産税や管理費がかかり続けます。
ステップ4:媒介契約の締結
査定に納得したら、不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約には3種類あります。
一般媒介契約
- 複数の不動産会社に同時に依頼できる
- 自分で買主を見つけることも可能
- 報告義務なし
専任媒介契約
- 1社のみに依頼
- 自分で買主を見つけることは可能
- 2週間に1回以上の報告義務あり
- レインズ(不動産流通機構)への登録義務あり
専属専任媒介契約
- 1社のみに依頼
- 自分で買主を見つけることも不可
- 1週間に1回以上の報告義務あり
- レインズへの登録義務あり
空き家売却ではどれを選ぶべきか
低価格の空き家の場合、専任媒介契約または専属専任媒介契約がおすすめです。
理由は、不動産会社が確実に報酬を得られる保証があるため、広告費をかけたり、積極的に営業活動をしてくれる可能性が高いからです。一般媒介では、他社で決まる可能性があるため、どうしても力の入れ方が弱くなりがちです。
契約時には、特例適用の承諾書にもサインします。報酬額、調査内容を必ず確認してください。
ステップ5:売却活動と成約
契約後は、不動産会社が以下のような活動を行います。
- レインズへの物件登録
- ポータルサイト(SUUMO、at home等)への掲載
- チラシの配布
- 現地看板の設置
- 内覧対応
売却活動中にできること
1. 簡易清掃
内覧前に最低限の掃除をしておくと印象が良くなります。
2. 写真映えを意識
カーテンを開けて明るくする、玄関周りを片付けるなど。
3. 定期報告を確認
問い合わせ件数、内覧数などを把握し、価格調整の判断材料にします。
空き家バンクの併用も検討
不動産会社の売却活動に加えて、自治体の空き家バンクへの登録も検討しましょう。
空き家バンクは、自治体が運営する空き家情報のマッチングサイトです。田舎暮らしを希望する人、移住希望者など、通常の不動産市場とは異なる層にアプローチできます。
登録は無料のことが多く、自治体によっては改修費用の補助金制度もあります。不動産会社経由での売却と並行して進められるため、売却チャンスが広がります。
売却以外の選択肢も検討すべき?
売却が必ずしも最善とは限りません。状況によっては、他の選択肢も検討する価値があります。
賃貸として活用する場合
メリット
- 定期的な収入が得られる
- 固定資産税を賃料でカバーできる可能性
- 将来的に相続人が使う可能性を残せる
- 管理を入居者に任せられる
デメリット
- 賃貸需要が少ない地方では入居者が見つからない
- 家賃が月2〜3万円程度と低い
- リフォーム費用が必要(最低でも50〜100万円)
- 入居者トラブルのリスク
- 固定資産税の減税措置が少ない
賃貸に向いているケース
- 建物の状態が比較的良い
- 駅やバス停、スーパーが徒歩圏内
- 学校や病院が近い
- リフォーム費用を回収できる見込みがある
私の経験では、地方の賃貸物件は入居者募集に半年以上かかることも珍しくありません。空室期間中も固定資産税や維持管理費はかかり続けるため、慎重な判断が必要です。
解体して土地として売る場合
建物が老朽化している場合、解体して更地にすることで売却しやすくなるケースがあります。
解体のメリット
- 建物の瑕疵(欠陥)を気にせず売却できる
- 買主が新築を建てやすい
- 土地としての価値が明確になる
解体のデメリット
- 解体費用がかかる(木造住宅で100〜200万円程度)
- 固定資産税が約6倍に増える(住宅用地の特例が使えなくなる)
- 解体しても売れる保証はない
解体費用と売却価格のバランス
例えば、解体費用が150万円かかる場合、更地にすることで売却価格が150万円以上アップするかがポイントです。
土地価格が200万円程度の場合、解体費用を負担すると手元に50万円しか残りません。それなら建物付きで100万円で売却した方が得、という計算になります。
解体は、以下のようなケースで検討すべきです。
- 建物が倒壊寸前で危険な状態
- 隣地に迷惑をかけている
- 買主が解体を条件にしている
- 土地需要が比較的ある立地
空き家バンクへの登録
前述した通り、自治体が運営する空き家バンクへの登録も選択肢の一つです。
空き家バンクの特徴
- 登録・利用は基本無料
- 移住希望者とマッチングできる
- 自治体の補助金制度を案内してもらえる
- 不動産会社の仲介と併用可能
自治体の支援制度
多くの自治体で、空き家の活用を促進するための支援制度があります。
- 改修費用の補助(上限50〜200万円)
- 家財処分費用の補助
- 固定資産税の減免
- 移住者への引越費用補助
ただし、補助金には条件があります。
- 一定期間以上の居住義務
- 賃貸の場合は家賃上限の設定
- 自治体への事前申請が必要
空き家バンクは、すぐに売却できるわけではありませんが、「誰かに活用してもらいたい」という思いがある方には適した選択肢です。
不動産歴40年が語る!実家売却でよくある失敗例
長年この業界にいると、多くの失敗事例を見てきました。同じ失敗をしないために、代表的なケースをご紹介します。
失敗例1:急いで相場より安く売却してしまった
Aさん(60代男性)のケース。
父親が亡くなり、地方の実家を相続しました。自分は都内在住で管理が負担だったため、「とにかく早く手放したい」と焦り、訪問してきた不動産買取業者に150万円で即決売却しました。
ところが後日、近所の方から「あの家、300万円で売りに出されているよ」と連絡がありました。買取業者がすぐに転売していたのです。
教訓
買取業者は転売目的で購入するため、市場価格の5〜7割程度の価格提示が一般的です。急ぐ場合でも、必ず複数社に査定を依頼し、相場を把握してから判断しましょう。
失敗例2:不動産会社任せで放置した結果
Bさん(50代女性)のケース。
母親から相続した実家を、地元の不動産会社に売却依頼しました。「お任せください」という言葉を信じて、その後は一切連絡せず半年が経過。
問い合わせると、「実は広告も出していませんでした。価格が安すぎて…」と正直に言われました。結局、別の不動産会社に切り替えて、3ヶ月で売却できました。
教訓
媒介契約を結んでも、積極的に活動しない会社もあります。定期報告をしっかり受け、問い合わせ件数や広告の掲載状況を確認しましょう。動きが鈍い場合は、契約期間終了後に別の会社に変更することも検討すべきです。
失敗例3:相続人間で意見がまとまらず時間だけが過ぎた
Cさん一家(兄弟3人)のケース。
父親の実家を兄弟3人で相続しましたが、長男は「思い出の家だから残したい」、次男は「すぐに売却したい」、三男は「賃貸にしたい」と意見が分かれました。
話し合いは平行線のまま2年が経過。その間も固定資産税は3人で分担し、年間15万円を負担し続けました。さらに建物は急速に劣化し、雨漏りが発生。最終的に売却を決めた時には、当初の査定額より100万円も下がっていました。
教訓
相続人が複数いる場合、早めに話し合いの場を設けることが重要です。感情的な対立を避けるため、第三者(税理士、司法書士、不動産会社)を交えた協議も有効です。
また、「誰が管理するか」「費用は誰が負担するか」を明確にしておかないと、放置されて劣化が進みます。
失敗例4:境界が不明確なまま売却しようとした
Dさん(70代男性)のケース。
山林付きの実家を売却しようとしたところ、境界杭が見当たらず、隣地所有者との境界が不明確でした。測量が必要と言われ、費用は80万円。
売却価格は200万円程度の見込みだったため、測量費用を引くと手元に残るのは120万円ほど。結局、隣地所有者に格安で買い取ってもらうことになりました。
教訓
境界が不明確な物件は、買主が住宅ローンを組めない可能性があり、売却が困難です。特に地方の広い土地や、山林が含まれる場合は、事前に境界確認をしておく必要があります。
測量費用が高額になる場合は、隣地所有者への売却も選択肢の一つです。隣地所有者なら境界問題が少なく、土地を広げたいニーズもあるため、スムーズに取引できることがあります。
私からのアドバイス
40年間、数多くの空き家売却に携わってきた経験から言えることは、「早めの決断と行動」が何よりも大切だということです。
空き家は時間が経つほど価値が下がります。建物は劣化し、草木は伸び放題、近隣からのクレームも増えます。「いつか考えよう」と先延ばしにするほど、選択肢は狭まっていきます。
完璧な解決策を探すのではなく、「現時点でのベストな選択」をすることが重要です。市場価格を受け入れ、適切なパートナー(不動産会社)を選び、前に進む。それが結果的に最も損失を少なくする方法なのです。
まとめ:相続した実家、今が売却のチャンス?
ここまで、相続した実家の売却について、低廉な空き家等の媒介報酬特例を中心に解説してきました。
特例制度を活用すれば可能性は広がる
「地方の古い家なんて売れない」と諦める必要はありません。2018年に創設された媒介報酬特例は、2024年7月にさらに拡充され、800万円以下の空き家でも不動産会社が積極的に仲介してくれる環境が整いました。
報酬の上限が33万円(税込)に引き上げられ、さらに売主・買主双方から報酬を受け取れるようになったことで、不動産会社にとっても採算が取れるようになり、より丁寧な現地調査や積極的な売却活動が期待できます。
特に、従来は対象外だった400万円超〜800万円以下の物件も新たに対象となったことで、より多くの空き家が流通する可能性が高まっています。
放置せず早めの行動を
空き家を放置すると、以下のようなリスクがあります。
- 建物の急速な劣化
- 固定資産税の継続的な負担
- 近隣トラブルの発生
- 特定空家に指定され、固定資産税が6倍に
- 相続人間の関係悪化
「今は忙しいから」「もう少し様子を見てから」と先延ばしにするほど、状況は悪化します。相続が発生したら、できるだけ早く現状確認と今後の方針決定をすることが大切です。
まずは専門家への相談から
売却するにしても、賃貸にするにしても、まずは専門家に相談することをお勧めします。
相談先の選択肢
- 地元の不動産会社:特例対応の確認と査定依頼
- 自治体の空き家相談窓口:補助金制度や空き家バンクの案内
- 司法書士:相続登記や権利関係の整理
- 税理士:相続税や譲渡所得税の相談
多くの自治体で無料の空き家相談会を定期的に開催しています。まずはそこで情報収集するのも良いでしょう。
あなたの次のアクションは?
この記事を読んだ今日から、次のアクションを始めてみませんか。
2. 地元の不動産会社2〜3社に査定を依頼する
3. 自治体の空き家相談窓口に電話してみる
4. 相続人が複数いる場合は、話し合いの日程を決める
5. 物件の現地写真を撮影しておく
思い出の詰まった実家を手放すことは、感情的にも簡単な決断ではないかもしれません。しかし、適切に次の持ち主に引き継ぐことも、大切な選択肢の一つです。
空き家を負担に感じているなら、まずは一歩踏み出してみてください。必ず道は開けます。
>相続した地方の実家 関連記事<