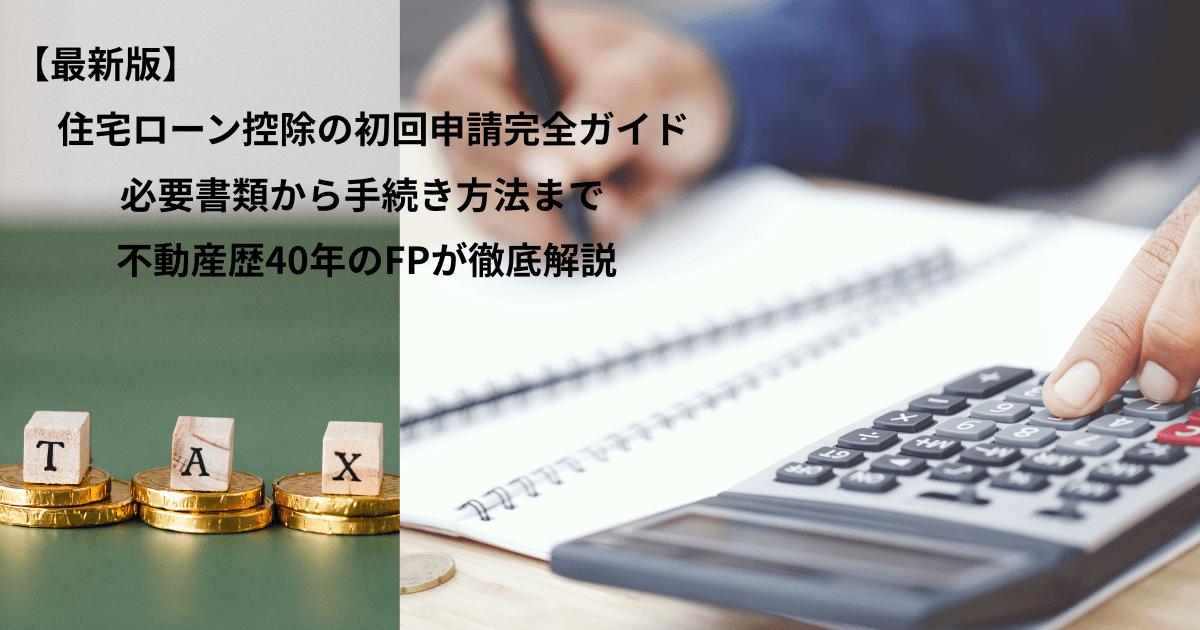リード文
住宅を購入し、いざ住宅ローン控除を申請しようと思ったとき、「何から始めればいいの?」「どんな書類が必要?」「手続きが複雑そうで不安…」そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
住宅ローン控除は、最大13年間にわたって所得税や住民税の控除を受けられる非常に有利な制度です。
しかし、初回の申請は確定申告が必要で、多くの書類を準備しなければならないため、手続きに戸惑う方が少なくありません。
私は不動産業界で40年以上の経験を積み、ファイナンシャルプランナーとして数多くのお客様の住宅ローン控除申請をサポートしてきました。
その経験から言えるのは、正しい知識と準備があれば、住宅ローン控除の申請は決して難しいものではないということです。
この記事では、住宅ローン控除を初めて申請する方に向けて、必要書類の準備から具体的な申請手順まで、わかりやすく丁寧に解説いたします。
最後まで読んでいただければ、迷うことなく住宅ローン控除の申請を完了できるはずです。
住宅ローン控除の基礎知識
住宅ローン控除とは?仕組みを分かりやすく解説
住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを購入または新築、増改築した場合に、年末のローン残高に応じて所得税や住民税から一定額を控除する制度です。
この制度の最大の特徴は「税額控除」である点です。
所得控除とは異なり、計算された税額から直接差し引かれるため、節税効果が非常に高いのが特徴です。
控除の仕組み
- 年末時点での住宅ローン残高を基準とする
- 住宅の種類や取得時期により控除率が決まる
- 控除額は所得税から差し引き、引ききれない分は住民税から控除
- 最大13年間(住宅の種類により10年間)継続適用
控除額と控除期間
住宅ローン控除の控除額と期間は、住宅の種類と取得時期によって大きく異なります。
新築住宅の場合
- 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅:年間最大35万円(13年間)
- ZEH水準省エネ住宅:年間最大31.5万円(13年間)
- 省エネ基準適合住宅:年間最大28万円(13年間)
- その他の住宅:年間最大21万円(13年間)
中古住宅の場合
- 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅:年間最大21万円(10年間)
- その他の住宅:年間最大14万円(10年間)
控除率は基本的に0.7%(借入限度額×0.7%)となっており、年末のローン残高に0.7%を乗じた額が控除額となります。
ただし、上記の年間最大額を超えることはありません。
※ 控除率0.7%、借入限度額内での年間最大控除額を表示
| 住宅の種類 | 新築住宅 年間最大控除額 | 中古住宅 年間最大控除額 | 控除期間 | 総控除額 (最大) |
|---|---|---|---|---|
| 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 | 35万円 | 21万円 | 新築13年 中古10年 | 新築455万円 中古210万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 31.5万円 | 21万円 | 新築13年 中古10年 | 新築409.5万円 中古210万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 28万円 | 21万円 | 新築13年 中古10年 | 新築364万円 中古210万円 |
| その他の住宅 | 21万円 | 14万円 | 新築13年 中古10年 | 新築273万円 中古140万円 |
緑色:省エネ住宅(控除額が優遇)|橙色:中古住宅
実際の控除額は年末ローン残高×0.7%で計算され、上記金額が上限となります。
実際の控除額は年末ローン残高×0.7%で計算され、上記金額が上限となります。